ブログをご覧の皆様、こんにちは!
いであるです!
「子どもが給食を食べられない」
「給食の時間がストレスで学校に行けなくなった」
など、給食が始まるこの時期は、多くの親御さんからご相談を受けています。
給食はお子さんの成長に必要な栄養を考慮して作られています。
しかし、「苦手なものが出る」「残せない雰囲気がある」
ということにプレッシャーを感じ、不登校のきっかけになることも少なくありません。
今回は給食が苦手で不登校になる前に家庭でできる対策について書いていきます。
給食がストレスで不登校に

「給食の時間が苦痛で仕方ない」
「苦手なものがあるのに、堂々と残せないのがつらい」
「食べるのが遅くて、昼休みまで食べさせられるのが嫌だ」
これは、小学生のお子さんを持つ親御さんからいただくご相談の中でも多い内容です。
決まった献立、決まった時間がある給食。
「好き嫌いが多い」「食感が苦手」「味に敏感」
このようなお子さんは、給食のルールに適応するのが難しく、精神的な負担が大きくなりがちです。
「好きなものだけ食べたい」「嫌いなものは食べたくない」という気持ちは、お子さんにとっては自然なこと。
しかし、給食は家庭の食事とは異なり、献立が決まっているため、どうしても食べたくないものも出てきます。
このギャップが 「学校に行きたくない」「給食の時間があるから不登校になる」 という状況につながってしまうことがあるのです。
家庭の食習慣が影響する?

「給食が苦手」というお子さんの家庭環境を見てみると、ある共通点があります。
それは 「家庭の食事がビュッフェスタイル」 になっているケースが多いことです。
ここでのビュッフェスタイルとは、大皿におかずを盛り、自分の好きなものを好きな量だけ取る食事スタイルのことを指します。
各家庭での食卓のスタイルはさまざまですが、 この食習慣が当たり前になっていると、学校の給食スタイルに適応しにくい傾向があります。
ビュッフェスタイルに慣れた子どもが感じるギャップ
・なぜ苦手なものを食べなきゃいけないの?
・食べたくないものを強制されるのがストレス…。
・好きなものを好きなだけ食べられるのが普通なのに…。
このように家庭と学校のギャップが大きくなることで、給食の時間が苦痛になり、不登校につながるケースも。

家庭でできる給食に適応できるようにするためのサポート

「給食スタイル」の食卓を意識する
(例)
・最初からお子さんのお皿に決まった分量を盛りつける
・「苦手なものもひと口は食べてみよう」と促す
・「おかわりは、まずは全部食べてから」とルールを決める
(※年齢により対応は変わります)
最初は食べ残しがあってもOK!
急にすべてを変えるのは難しいので、少しずつ取り入れていきましょう。
「目の前にあるものを食べる」という環境をつくることが大切です。
「食べないよりは好きなものだけでも…」の考え方をやめる
「好きなものだけでも食べてくれればいい…」という考え方は、お子さんの成長にとってマイナスになることもあります。
・ 「好きなものだけ食べる」 → 給食の時間がストレス
・「家庭では食べなくてもOK」 → 学校でも食べたくない
これが 「給食が嫌だ→学校に行きたくない」 という悪循環を生む原因になります。
「せっかく作ったのに残されると悲しいな」など、 親の気持ちを伝えることも効果的です。
食事の献立は親が決めてOK!
毎日の食事メニューは、基本的に親が決めてしまって問題ありません。
もちろん、誕生日や特別な日はお子さんのリクエストを取り入れるのは良いことです。
しかし、普段の食事をお子さん主体で決めすぎると、学校での適応力が下がる可能性が大いにあります。
「今日は〇〇が食べたい!」 → いつも希望を叶えるとワガママに
「苦手なものは出さない」 → 外食や給食で困ることに
家庭のルールをしっかり決めることで、お子さんが社会のルールにも順応しやすくなります。
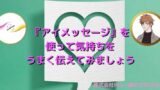
【まとめ】給食が不登校の原因になる前に家庭でできること

・給食が苦手な子どもは「家庭の食習慣」に原因があることも
・ビュッフェスタイルに慣れていると、給食のルールがストレスに
・「決まった食事を食べる」環境を家庭でつくることが大切
・親が食事のメニューを決め、苦手なものにも少しずつ慣れていく
学校と家庭の食習慣に大きなギャップを作らないことが、 「給食がストレスで不登校になる」リスクを減らすカギとなります。
今日から少しずつ取り入れてみてください。
PLSでは、不登校の復学支援だけでなく、日頃から子育て全般のご相談を受けています。
お子さんが不登校ではないという場合でも、
・「もっと子育てを楽しみたい」
・「我が子に合う子育てを学びたい」
・「ひとりで子育てするのがつらい」
という親御さんは一度、ご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回のブログでお会いしましょう。


活動範囲
PLSの復学支援は、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州と全国対応しています。
訪問支援の実績がある地域
これまでに以下の地域へ訪問し、対面での復学支援を行ってきました。
北海道
東北/宮城県 山形県 福島県
関東/茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 長野県
北陸/新潟県 富山県 石川県 福井県
中部/静岡県 愛知県 三重県
近畿/滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国/岡山県 広島県
四国/徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州/福岡県
沖縄
にほんブログ村
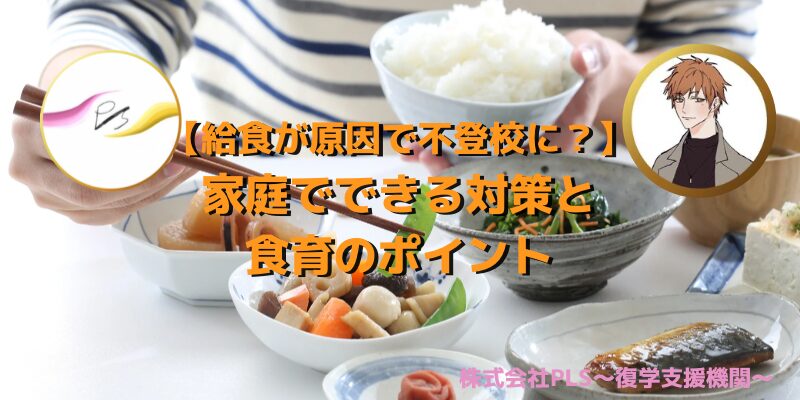


コメント