ブログをご覧の皆様、こんにちは!
いであるです。
近年、不登校児童の増加が深刻な社会問題となる中で、復学支援の重要性が改めて議論されました。
今回は、先日京都府で開催した「復学支援会議」についての報告です。
・不登校のリスクとは?
・復学支援の必要性と課題
・復学支援が悪と捉えられる理由
・復学支援が求められる家庭とは?
これらのテーマを詳しく解説します。
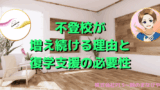
復学支援会議の概要

【開催地】 京都府
【参加者】 教育関係者4名
【議題】
① 近年の「不登校のリスク」について
② 「復学支援」のアップデート
③ 「復学支援」が悪と捉えられることについて
④ 「復学支援」に求められることについて
新年度が始まる4月は、不登校に悩む家庭が急増する時期です。
そのため、今のうちに「予防策」を考えることが大切です。
復学支援の相談件数は、4月〜5月にかけて急増する傾向にあります。
その背景には、「不登校が続いたまま進級・進学することへの不安」があるためです。
① 不登校のリスクとは?

不登校に対する考え方は様々ですが、共通しているのは「将来への不安」です。
不登校のお子さんや親御さんの多くは、ネットやSNSで「不登校でも大丈夫」という情報に安心感を得ることがあります。
その瞬間は「大丈夫!」と思ってしまっても、携帯を閉じて我が子を目の前にするとやっぱり「はぁ…将来が不安」と割り切れない日々を過ごされている親御さんが多いです。
現実問題として、不登校のまま年齢を重ねたときのリスクを無視することはできません。
不登校のリスクとして考えられること
・引きこもりの長期化 → 進学や就職が困難に
・成長の機会を失う → 社会性の欠如
・8050問題のリスク → 大人になっても自立できない
「8050問題」とは、50代の親が80代になっても、引きこもりの子どもを支え続ける社会問題のことです。
この深刻な課題を防ぐためには、早期解決の復学支援が求められます。
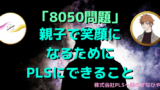
② 復学支援のアップデート

「復学支援」とは、不登校のお子さんが学校に戻れるようサポートする仕組みです。
不登校が長引けば長引くほど、学校復帰の難易度は上がります。
例えば、
・小学生の不登校 → 早期対応で解決しやすい
・中学生の不登校 → 思春期の影響で難易度が上昇
・高校生以上の不登校 → 学校復帰が困難になるケースが増える
このように年齢が上がるにつれて、状況は複雑になることが多いです。
実際、高校生の復学支援を行う機関は少ないのが現状です。
しかし、何の対策もせずに成人を迎えてしまうと、社会復帰の難易度はさらに高まります。
以前PLSの復学支援である「高校生サポートプラン」をブログで紹介しましたが、高校生は義務教育も終了しているため、全てのお子さんに適用できるわけではありません。
どのご家庭にも柔軟に対応することを心掛けているPLSでも、高校生となると一筋縄にいかないのが現実です。
私たちは各学校と直接連携をとり復学準備を進めることも少なくありません。
その際に校長先生や担任の先生でさえ「さすがに高校生で今から復学は無理では…」と諦めの声を聞くことも多々。
PLSでも高校生のお子さんの不登校相談となれば、とても慎重になります。
全てを受け入れられるわけではないですし、専門領域ではないと判断すればお断りすることも。
しかし、そのご家庭の将来のことを思うと、何か一歩を踏み出す形でサポートできないかという話をし、以下の取り組みにより一層力を入れていくことになりました。
高校生の復学支援の拡充
→高校生の復学支援は特殊ではなく、「当たり前の支援」として広めるべくこれまでも活動してきました。
しかし、PLSでは受け入れ態勢が整ってきていますが、まだまだ高校生のハードルの高さを懸念される不登校支援機関が多いように見受けられます。
関わりある支援者、教育者には高校生の支援の必要性をアプローチしていきます。
復学支援の認知度向上
→ここ数年で復学支援という言葉は、少しずつ認知されつつありますが、それでも「復学支援って何?」「復学支援なんて初めて聞いた」「何か怪しそう…」という意見の方が圧倒的に多いです。
SNSなどを通して幅広く認知活動をしていきます。
相談件数の増加に対応
→支援を希望されるご家庭が増加する中で、受け入れ体制の強化も不可欠です。
こちらは過去何度か復学支援会議をしていく中でも特に重視される部分です。
「取りこぼしのない支援」「手の届く親子は全員救う」という理念により支援の枠数は年々増幅させています。
③ 復学支援が「悪」と捉えられる理由

「復学支援がやばい」など、悪と捉えられる理由について、本会議では以下の意見が出てきました。
あくまでも、数多くのご家庭を支援してきた“支援者目線”に基づくものであり、必ずしも全ての人が同意するわけではないことを前提としています。
・子どもの意思を無視する可能性
復学支援は不登校や休学中の人が学校に戻ることをサポートするものですが、本人が学校に戻りたくない場合でも、無理やり復学を強制される形になることがあります。
これが個人の自由や感情を軽視していると見なされ、悪と捉えられることがあるように見受けられます。
・一律的な価値観の押し付け
「学校に戻ることが正しい」という前提が復学支援には含まれがちです。
しかし、全てのお子さんや親御さんにとって学校が最適な場所とは限りません。
学校に代わる学びの場や自己実現の道を否定するような姿勢が、悪とみなされる理由になり得ます。
怠けで学校に行かない、学校に行きたいけれど戻りづらいというケースとは別で、精神的負担など復学以外の選択肢が必要なケースも多々あります。
・精神的な負担の増大
復学を目指す過程で、不登校の原因(いじめ、学習困難、精神的な問題など)が十分に解消されないまま学校に戻されると、本人のストレスや不安がさらに悪化する可能性があります。
この結果、支援がむしろ害を及ぼすと捉えられることがあります。
実際にPLSの支援を受ける前に「背景関係なく復学を促された結果、子どもへの精神的負担がかかり外に出られなくなった」という相談も受けたことがあります。
お子さんの様子を見て「やはり復学支援をすべきではなかった」と思う親御さんもおられるのでしょう。
・高額な費用面
復学支援が民間企業や団体によって行われる場合、高額な費用がかかるケースがあります。
各支援機関により料金形態は変わりますが、PLS含めて「訪問型」になるとカウンセリング料だけでなく交通費などもかかるため決して安価にならないことが多いです。
費用面の印象からも、やばいと言われてしまうこともあるようです。
・問題の根本解決を後回しに
復学支援が「学校に戻ること」をゴールに設定しがちなため、不登校や休学に至った背景(家庭環境、学校制度の不備、社会的圧力など)の根本的な問題解決が置き去りにされることがあります。
親御さんの「とにかく学校に戻ってほしい」にのみフォーカスして、お子さんの背景を細かく分析せずにノウハウのみで学校へ仕向ける。
これが表面的な対応として悪と評価される理由にも見受けられます。
上記理由は、復学支援の目的や実施方法次第で変わるため、必ずしも全ての「復学支援機関」に当てはまるわけではありません。
このように、「復学支援=無理やり学校に戻すもの」と誤解されてしまうことがあります。
しかし、PLSの復学支援の本質は「子どもの気持ちに寄り添いながら、学校に行けるようサポートすること」です。
復学支援が必要なのは、以下のようなケースです。
「本当は学校に行きたいけど、行けない」
「学校に戻る方法がわからない」
「復学したいけど、親が対応に困っている」
「学校が好きなわけではないけど、このままでは良くないと思っている」
復学支援は、「学校に行きたくない」と心から強く思っているお子さんを無理に学校へ戻す支援ではありません。

④ 復学支援を求める家庭とは?

「学校に行きたくない」と心から思っているお子さんに復学支援が必要無いのと同じように、「学校なんてこの子の将来に必要ない」「別に不登校でもなんとかなるし、なんとかしてみせる」と考えるご家庭には、復学支援は必要ありません。
しかし、
「本当は学校に行きたい」
「でもどうしても行けない」
「親もどう対応すればいいかわからない」
というご家庭には、復学支援が最適な選択肢となります。
親御さんの中には、「うちの子は『学校に行くもんか』と言っているから、もう無理かもしれない…」と感じてしまうこともあるかもしれません。
しかし、お子さんの本心は違う可能性があります。
これまで数え切れないほどの不登校のお子さんと出会ってきましたが、「行きたいけど行けない」というお子さんばかりです。
「二度と学校には行かない」というお子さんには出会ったことがありません。
「本当は行きたいのに、行けない」
「引きこもり続けている生活がダメだとは分かっている」
この気持ちを見逃さず、本心に向き合い、その上で解決方法を一緒に考えることが大切です。
まとめ

今回の復学支援会議では、
・不登校のリスクと将来への影響
・高校生以上の復学支援の必要性
・復学支援の誤解を解消する取り組み
・本当に支援を必要としている家庭へのアプローチ
について議論しました。
まだまだ「復学支援」という言葉が広く知られているわけではありません。
しかし、「親子が笑顔で過ごせる未来」のために、「親子で笑顔になるために」PLSの復学支援は重要な役割を果たします。
私たちはこれからも定期的に復学支援会議を開催し、必要な支援を届けるための活動を続けていきます。
最後までご覧いただきありがとうございました。
次回のブログでお会いしましょう。


にほんブログ村
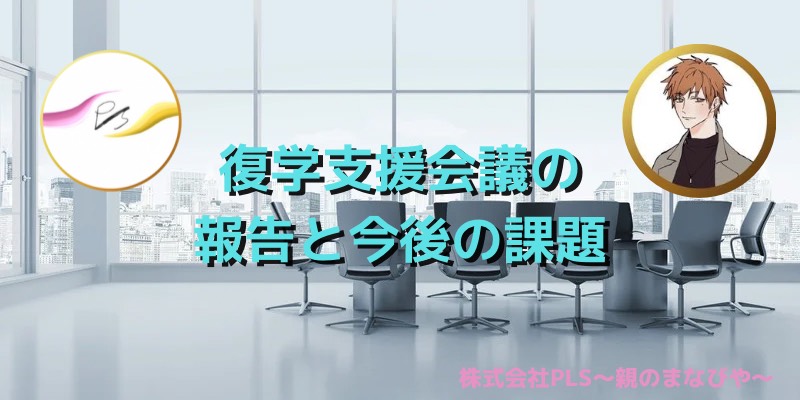
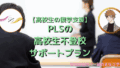

コメント