ブログをご覧の皆さま、こんにちは!
いであるです。
不登校のお子さんの日常は、実際に経験しなければ分からないことも多いです。
訪問カウンセラーが寄り添うことで、変わる状況。
ブログに書ける範囲になりますので、ごく一部ですがご覧ください。

不登校のお子さんは、どんな日常を過ごしているのか

不登校のお子さんの日常生活とはどういったものだと思いますか?
実際に私が見てきた事例では、
・お風呂に入らない。
・毎日部屋に閉じこもってゲームをする。
・家族のみんなが寝静まった後にリビングに降りてきて食事をしたりお風呂に入る。
・生活リズムの乱れによる昼夜逆転傾向がある。
・勉強をしない、ペンすら握れない。
・家族に手を出してしまうような暴言暴行がある。
・学校に登校できていないことを家族のせいにする。
・自室にバリケードを作って誰も入れないようにする。
・部屋が好き放題散らかっている。
・部屋の壁が穴だらけ。
・他責思考傾向がある。
・自分が登校できていないことに罪悪感を覚えて極端な自責思考がある。
など、お子さんにより様々です。
学校に登校していた時とは全く違う行動を取ることが多い傾向にあります。
家族や親戚以外においては最低限のコミュニケーションしかとらなくなってしまいます。
不登校中のお子さん自身が「この行動は不必要」と判断すると、行動に移さないことが多いです。
誰かに会うわけではないので、髪の毛や爪は伸び放題で、お風呂にも入らず、漂う体臭も部屋に充満、肌は少しずつ黒ずんでしまう…。
このように、性別を問わず、身だしなみを整える必要性すらも感じなくなりやすいです。
そうなれば余計に誰かと会うことを遮断してしまいます。
ケースによっては家族とすら顔を合わせたがらないお子さんもいます。
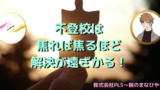
不登校のお子さんが訪問カウンセラーと出会うと…

不登校のお子さんが訪問カウンセラーと出会うと、これまでの家での過ごし方が少しずつ改善していきます。
その理由には、家族以外の第三者と会う機会ができるからということもあります。
それよりも、お子さん自身が訪問カウンセラーとの距離感を考えるようになるからです。
訪問カウンセラーは心理学的観点から見ていきます。
お子さんの心に寄り添うテクニックや、お子さんの趣味や興味にも合わせる技術を持っているのです。
なので、多面的に見て「この人に任せたら自分も頑張れるかもしれない」と考えるお子さんが多いように感じます。
このような心境の変化を促すことで、少しずつ復学に向けて生活リズムを整えるようになっていくのです。
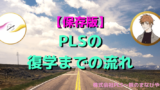
不登校のお子さんと接する訪問カウンセラーの役割とは

不登校のお子さんは家族以外の人と会うことが少ないです。
そのため、第三者である訪問カウンセラーの介入により、これまでの家庭内での生活のリズムが一変することがほとんどです。
では、お子さんは訪問カウンセラーと出会うことにより、どのような影響が出るのでしょうか。
カウンセラーがご家庭に訪問することにより、多くのお子さんが前向きな気持ちに切り替えることができます。
さらに、家庭内での親子関係も再構築できるようになるケースが多いです。
訪問カウンセラーとお子さんの信頼関係(リレーション)の構築をしていく。
そして、親御さんのお子さんとの関わり方における注意点を、お子さんの性格傾向を交えて分析します。
その結果を、担当カウンセラーが親御さんにアドバイスをする。
これにより、親子の距離感の改善を促しているということが大きいです。
訪問カウンセラーの介入だけでは、カウンセラーがその場にいる時だけの変化になってしまいます。
家庭を変えるためにはカウンセラーが訪問していない時の“親御さんの対応”がポイントとなります。
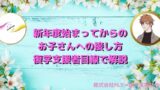
不登校のお子さんが訪問カウンセラーと出会って変わる姿

訪問カウンセラーは、家庭全体を客観的に見ています。
だからからこそ親御さんにできるアドバイスがあるのです。
私たちPLSで言う“完全カスタムメイド型”の支援になります。
また、訪問カウンセラーがお子さんと信頼関係を構築することで、復学に向けた準備をお子さん自ら率先して行動することもあります。
訪問カウンセラーとの出会いにより、不登校中の生活リズムから気持ちを切り替えができる。
さらには、より良い私生活を過ごせるようにしようと考えているのかもしれません。
私が訪問してきたご家庭のお子さんの多くが次のように話してくれます。
「本当は学校に行かないといけないことはわかっていた。」
「行きたいけど行けなかった。」
このように、訪問カウンセラーとお子さんが出会うことで学校に対する気持ちと向き合う“きっかけ”になっていると言えます。
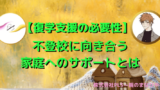
不登校のお子さんが訪問カウンセラーと出会ってからの変化【まとめ】

暖かい気候になるにつれて、外出しやすくなるお子さんもいれば、のほほ〜んとしてしまい、のんびりしてしまうお子さんもいます。
そんな中でも、訪問カウンセラーと接することでお子さんは変わり始めます。
PLSではお子さんの復学や、家庭教育観点から親御さんとお子さんの関わり方のアドバイスなど、各家庭の悩みに合わせた支援を行っています。
ご家庭のことで悩まれていることがありましたら、お気軽にご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
それでは、次回のブログでお会いしましょう。
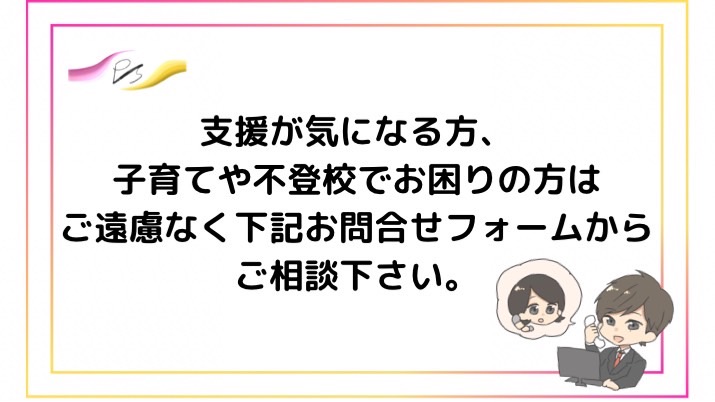

にほんブログ村
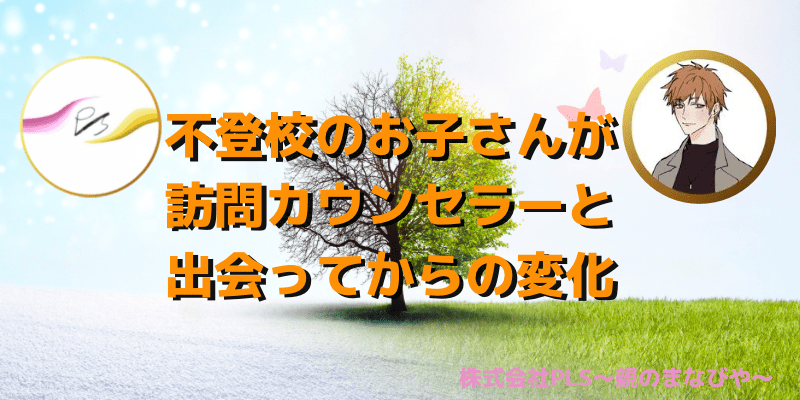
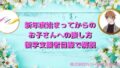
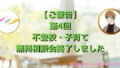
コメント