ブログをご覧の皆様、こんにちは。
いであるです。
家庭では元気そうに見えるのに、朝になると学校へ向かえない。
PLSには、この「元気に見える不登校」の相談が後を絶ちません。
外からは「元気なのに甘えているだけでは?」と誤解されてしまいがちですが、元気に見えることと、学校に行けることはまったく別の問題です。
家庭では安心できても、学校という環境になると負担が一気に高まり、心と体がストップしてしまうケースは珍しくありません。
この記事では、元気に見える子どもが抱える見えない負担、家庭でできる関わり方、そして早期に専門家とつながる重要性について解説します。
元気に見える不登校の子が抱える見えない負担

元気に見える子どもほど、学校に行けない理由は複雑です。
PLSが相談を受けるお子さんには、以下のような共通点があります。
家では元気でも、学校への不安が強い
家庭は安心できる空間のため笑顔を見せますが、学校では人間関係・教室の空気・授業の進度など、多くの不安が重なります。
登校の直前になると緊張で体が動かなくなる子もいます。
親に見せないストレスや緊張がある
「心配させたくない」という気持ちから、本音を隠す子は少なくありません。
元気に見えても、胸の内では不安がパンパンに膨らんでいることがあります。
小さな失敗体験が、次の一歩を止める
一度の欠席が「もう行けないのでは…」と自己不信につながり、登校のハードルがさらに高くなることがあります。
これが積み重なると、元気に見えても急に動けなくなることにつながります。
学校に行けないのは甘えではない

元気に見える子ほど、限界まで頑張った結果としてストップがかかることがあります。
不登校は、気持ちややる気の問題ではありません。
限界まで頑張った結果のストップ
元気に見える子ほど、実は毎日ギリギリまで努力しているケースがあります。
朝だけ動けないのは、心・体が限界を迎えたというSOSです。
家ではリラックスできるが、学校では負荷が大きい
環境が変わるだけで状態も大きく変わります。
家で笑顔でも、学校では不安が強く出るのは自然なことです。
無理に行かせると逆効果になることも
「今日こそ行きなさい」と追い込むと、不安がさらに増大し、登校自体がより困難になる場合があります。
まずは安心できる環境の確保が最優先です。
家庭でできるサポート方法

元気に見える不登校の子どもに対して、家庭でできるサポートは次の通りです。
子どもの気持ちを、安心して話せる場をつくる
「どうして行けないの?」と理由を詰めるのではなく、子どもが「話しても否定されない」と感じられる関わりが大切です。
生活リズムを整える
朝の起床時間、食事、学習や遊びの時間を少しずつ整えることで、心身の安定を促します。
規則正しい生活は、登校への心理的準備にもつながります。
無理に登校させず、焦らず見守る
行ける準備ができるまで焦らず見守りましょう。
失敗しても責めず、安心できる環境を維持することが重要です。
専門家と連携してサポート
PLSでは家庭・学校・支援者と連携し、子どもに合わせた復学支援プランを提供しています。
専門家のサポートを活用することで、無理なく学校復帰の準備を整えることができます。
早期支援の重要性

学校に行けない状態が長引くと、学習や人間関係の不安が積み重なり、後から取り戻すのが難しくなります。
早期に支援を始めることで、子どもは自分のペースで少しずつ前に進む準備ができます。
• 不登校の長期化による学習遅れの予防
• 不安の可視化と心理的サポート
• 家庭内での安心感の維持
これらは、学校復帰への土台作りに不可欠です。

まとめ:元気に見える不登校の子どもへの対応

元気に見える子どもほど、学校に行けない背景は複雑です。
PLSでは、家庭でのサポートと専門家の支援を組み合わせ、安心して学校復帰できる環境を整えます。
• 家庭で安心感を作る
• 小さな成功体験を積ませる
• 専門家と連携する
まだ学校に行けていない状態でも、焦らず少しずつ前に進める方法があります。
全国対応で、お子さん一人ひとりに合わせた復学支援プランをご提案します。
今、お子さんの不登校でお悩みの親御さん、一度ご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
次回のブログでお会いしましょう。


活動範囲
PLSの復学支援は、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州と全国対応しています。
訪問支援の実績がある地域
これまでに以下の地域へ訪問し、対面での復学支援を行ってきました。
北海道
東北/宮城県 山形県 福島県
関東/茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 長野県
北陸/新潟県 富山県 石川県 福井県
中部/静岡県 愛知県 三重県
近畿/滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国/岡山県 広島県
四国/徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州/福岡県
沖縄
にほんブログ村
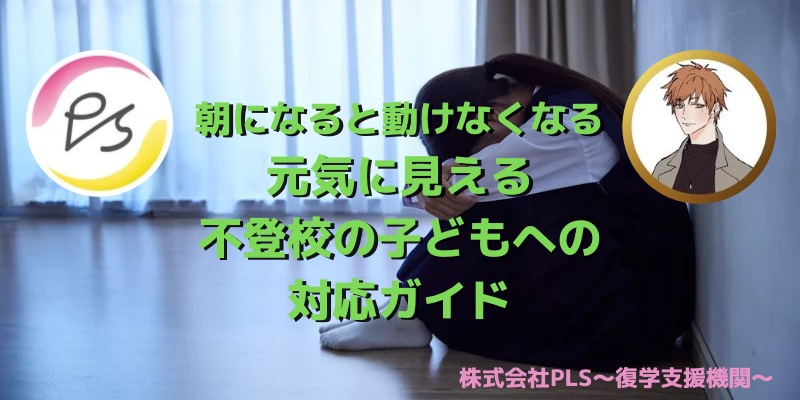
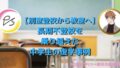

コメント