ブログをご覧の皆様、こんにちは!
いであるです。
今回は、不登校から復学した子どもたちが直面しやすい「宿題」の問題について、復学支援の現場からリアルなお話をご紹介します。
「うちの子、宿題ができなくて困っている…」と感じる親御さんには、ぜひ読んでいただきたい内容です。
復学後にぶつかる「宿題の壁」

不登校から復学するということは、単に学校に戻るだけではありません。
日常生活を取り戻し、学校生活に慣れていく過程でもあります。
その中で、多くのお子さんが最初にぶつかるのが宿題です。
無理をさせず登校リズムを優先
復学直後のお子さんに「宿題をしなさい」と強く求めることはしません。
学校に通うだけでも大きなエネルギーを使うためです。
「しばらくは宿題ができなくても大丈夫。まずは学校に行くことが一番大切だよ。」
この声かけを通じて、登校リズムを整えることを最優先にします。
この段階での目標は、頑張ることではなく、学校に戻る感覚を取り戻すことです。
避けて通れない「宿題の後回し」
登校が安定してくると、次の課題として宿題への取り組みが必要になります。
提出状況は成績や内申点に影響することもあり、学校生活で避けて通れない現実です。
ただし、不登校のお子さんにとって宿題の習慣は簡単には戻りません。
• 勉強が怖い
• 内容を忘れた
• わからない
• やる気が出ない
こうした理由で宿題が後回しになるケースは珍しくありません。
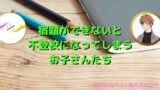
まずは「提出すること」を目標に

訪問カウンセラーとして、登校に慣れてきたお子さんにはこう伝えます。
「宿題は答えを写してもいい。まずは提出することが大事だよ。」
ここでのポイントは、完璧を目指すのではなく、未完成でも「出せた!」という成功体験を積ませることです。
完璧主義のお子さんほど、宿題が完成しないことで登校に影響が出るケースが多いため、まず提出する力を育てることが重要です。
提出できた経験は、自己肯定感の向上にもつながります。
家庭と学校の連携が鍵

宿題に取り組めるようになるには、家庭・カウンセラー・学校の三者連携が不可欠です。
• 学校の先生が提出状況を確認し、必要に応じて注意やサポートを行う
• 家庭では声かけや学習環境の整備を行う
• カウンセラーが家庭と学校の橋渡しをして、方向性を揃える
こうしたサポートにより、お子さんは「やるべきことはやる」という感覚を少しずつ取り戻していきます。
宿題の本当の意味は「続ける力」

宿題は単なる勉強課題ではありません。
日常生活のリズムを取り戻し、社会生活に再びなじむための練習でもあります。
• 最初は答えを写してもOK
• 大事なのは「出せた」「続けられた」の積み重ね
• それが学校生活を自分の力で歩む心の力を育てる
復学支援の現場では、お子さんが「できない」から「やってみよう」に変わる瞬間を何度も目にしてきました。
その小さな一歩こそが、お子さんの成長の始まりです。
まとめ

・不登校から復学した子どもが直面する最初の課題のひとつは「宿題」
・まずは無理をさせず、登校リズムを整えることが優先
・完璧を求めず、提出することを成功体験として積む
・家庭・学校・カウンセラーの三者連携が成長を支える
・宿題は「学習」だけでなく「続ける力」を育む重要なステップ
お子さんの再スタートは、小さな一歩の積み重ねです。
宿題を通じて「やればできる」という自己肯定感を育てることが、学校生活を取り戻す大きな力になります。
今、お子さんの不登校でお悩みの親御さん、一度ご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
次回のブログでお会いしましょう。


活動範囲
PLSの復学支援は、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州と全国対応しています。
訪問支援の実績がある地域
これまでに以下の地域へ訪問し、対面での復学支援を行ってきました。
北海道
東北/宮城県 山形県 福島県
関東/茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 長野県
北陸/新潟県 富山県 石川県 福井県
中部/静岡県 愛知県 三重県
近畿/滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国/岡山県 広島県
四国/徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州/福岡県
沖縄
にほんブログ村



コメント